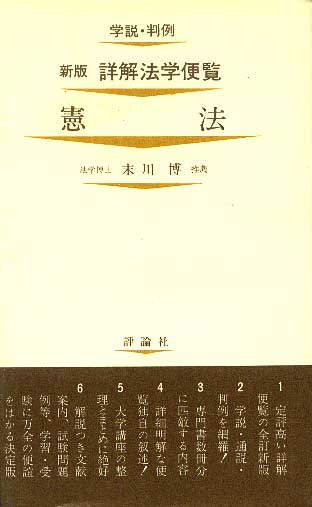
明治憲法は、一八八九年(明治二二年)に「不磨ノ大典」として制定公布されてから五七年間、かつて一度も改正されたことがなかった。その理由は、一つにはその規定がきわめて簡潔であって弾力的な解釈が可能であったこと、二つには特に改正を必要とする重大な政局に当面しなかったことにあるとされている。しかし太平洋戦争終結の結果、形式的には「帝国憲法の改正」(日本国憲法上諭)という手続をとったが、実質的には、明治憲法とは全く異なった新しい「日本国憲法」が制定されるに至ったのである。
改変の外部的原因となったのは、敗戦に基づくポツダム宣言の受諾である。わが国は、一九四五年(昭和二〇年)八月一四日ポツダム宣言を受諾して、太平洋戦争を終結せしめたのであるが、その結果、この宣言の条項を忠実に履行すべき義務を負うことになった。.そして同宣言の中には、「日本国政府は日本国国民の間に於ける民主主義的傾向の復活強化に対する一切の障礙を除去」すべきこと(一〇項)、「言論宗教及思想の自由並に基本的人権の尊重は確立せらる」べきこと(一〇項)、および「日本国国民の自由に表明せる意思に従い平和的傾向を有し且責任ある政府が樹立」さるべきこと(一二項)が要求されていた。ところで、明治憲法もまた民主主義的要素を多分にとり人れていたので、その運用のよろしきを得さえすれぽ、ポツダム宣言の条項を実施する目的はこれを達成することができるから、必ずしも明治憲法を改正する必要はないという見解[美濃部達吉・憲法改正問題「昭和二〇・一〇・二〇朝日新聞」所載]もあった。しかし、明治憲法は天皇制を申心とする絶対主義的な要素が強かったので、ポツダム宣言の要求を忠実に履行するためには、その根本的な改正を行なわざるをえないという意見が強くなったのである。
改変の内部的原因となったのは、自由主義的政治思想の世界史的な潮流に基づく日本国民自身の自覚的かつ自発的な要望であった。すなわち、久しい間にわたって軍部と官僚の専制圧迫に悩まされ続けてきた日本国民が、その解放とともに、自由と権利を保障する新日本再建のための基本法の制定を強く要望するに至ったからである。
上記に引用した文章は、前半は大體正しい。しかし、後半は大嘘である。
良く知られてゐるやうに、實際の「改正」の作業に際しては、G.H.Q.の意嚮が強く働いてをり、日本国民自身の自覚的かつ自発的な要望
があつたのではない。
斯うした事實の歪曲は長い間、「正統の解釈」として法學の世界を支配してゐた。現在も中學校や高校の「公民」等の授業ではこの「解釈」が通用してゐると小山常実氏が報告してゐる(『公民教科書は何を教えてきたのか』(展転社))。
(1) 問題の所在 日本国憲法の制定は、実質的には新憲法の制定であったにもかかわらず、形式的には明治憲法の改正として行なわれた。そこに種々の困難な問題が生ずるのである。
明治憲法は、その第七三条において改正の手続を規定して、一面「不磨ノ大典」(旧憲法発布勅語)とは称したものの、反面「将来……憲法ノ或ル条章ヲ改正スルノ必要」(旧憲法上諭五段)あるべきことを予定しないではなかったのである。しかし、その予定したところは、あくまでも「憲法ノ或ル条章ヲ改正」すること、すなわち一部改正であったのであって、その根本的な全面改正ではなかった。いわんや「国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ」(旧憲法上論二段)とする天皇主権の国体的な原理は、学説上一般に改正可能の範囲外とされていたのである。しかるに日本国憲法は、ただにその名称を変更したぱかりではなく、革命的に国民主権の建前をとり、かつ条文の全体にわたってその内容を根本的に改変したのである。したがって、日本国憲法の制定をもって、はたして明治憲法第七三条の規定に基づく同憲法の改正と称しうるかどうかが問題とされるわけである。
日本国憲法の制定にあたっては、前述したように、明治憲法第七三条の規定によってその手続が進められ、枢密院への諮詢、天皇の発議、帝国議会の議決、天皇の裁可という一連の手続を経たわけである。上諭も、「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至ったことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。」といっている。しかるに、日本国憲法の前文は、「日本国民は、……ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」といって、その民定憲法たる旨を明らかにしている。したがって、この形式的欽定性と実質的民定性との矛盾がやはり問題とされなけれぱならないのである。
(2) 問題の解決 これらの問題については、事の形式性に重きをおくか、あるいは実質性に重きをおくかによって結諭が違ってくるのであって、おおむね次のような三つの考え方がある。
(イ) 欽定憲法説――故佐々木博士は、「日本国憲法が内容上、帝国憲法を全面的に変更するものであっても、その故に、その変更を目して革命といい、その憲法を目して革命による憲法、といい得ない……」とされ、「日本国憲法は前述の如く、帝国憲法第七十三条の定めるところの、天皇の提案、帝国議会の議決、天皇の裁可という行動により、成立したのである。即ち、日本国憲法は天皇が制定したもうたのである。故に、日本国憲法は欽定憲法である。」とされた[佐々木一一三頁〜一一四頁。なお、大石八五頁・九七頁]。そして、日本国憲法前文に「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、……ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」というのは、「帝国憲法施行時に、帝国議会が帝国憲法改正案たる日本国憲法案を議決した、という事実に関していうのではない。日本国憲法の成立後において、主権在民であること、及び、日本国憲法が国家の根本法とせられること、をいうのである。」とされ、「故に、……前文の文言に、天皇が、帝国議会の議決を経て、帝国憲法を改正する日本国憲法を制定せらせた、という、目本国憲法成立前の国家事象を、対照せしめて考え、右の前文が事実に合うや否やを問題とすることをしてはならぬ。」と主張された[佐々木一四七頁]。
しかしながら、憲法の改正をもって主権の所在を変更することはできないと解する以上、この説をとることはできない。それに、前文の「日本国民は、……ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」という言葉を、将来に向かっての規範的な意味にだけ受け取って、「事実に関していうのではない。」とされる点にも納得しえないものがある。
(ロ) 条約憲法説――この説は、日本国憲法の制定過程において連合軍司令部の強力な指導や勧告が加えられたという事実に着目して、日本国憲法を一種の条約憲法とみる考え方である。すなわち、「右のような諸関係に着目するかぎり、日本国憲法は純粋に日本国民だけで制定を完了した憲法ということはできない。それは、むしろ日本国と連合国との協同行為を基礎とした一種の条約憲法と見る方がふさわしいであろう。それは連邦国家のいわゆる国定憲法もしくは条約憲法とは、もとより異なるものではあるが、米ソ両陣営の妥協を背景とした連合国と日本国政府との協定にもとづく新しい型の条約憲法と見ることが可能であろう。」とされる
のがそれである[黒田一六八頁]。
(ハ) 民定憲法説――この問題を解決するためには、ポツダム宣言の受諾によって、天皇主権の建前が放棄されて新たに国民主権の建前が確立され、天皇の性格が一変したものと考えなけれぽならない。ポツダム宣言は、「日本国国民の自由に表明せる意思に従」(一二項)ってその統治形体が定められるべきことを要求していたのであるが、わが国はこれを受諾したのであるから、これによって、日本国民は新たに主権者たるの地位を取得し、憲法制定権力者として自由に新憲法を制定しうることになったのである。したがって、ポツダム宣言の受諾は、明治憲法の基本的原理を根本的に覆した革命的な行為とみるべきであって、天皇は、国民あっての天皇となり、もっぱら国民の象徴となったのである。日本国憲法は、天皇の発議・裁可という手続をふんで制定されたものであるが、それは、国民の象徴となった天皇が、国民の総意を反映しつつ発議し裁可したものにほかならない。したがって、手続上の形式的欽定性は実質的民定性を反射するにすぎないものとなり、その中に吸収されてしまって実は欽定的なも,のではなかったということになるわけである。また、ポツダム宣言の受諾によって、明治憲法における天皇主権の建前が放棄されたとすれば、それを前提とする改正の限界という問題も無意味となり、ここに全面的な改変が可能とされたわけである。要するに、日本国憲法制定の手続が帝国憲法第七三条の規定に準拠したのは、両憲法の時間的継続性を意図した手続上の便宜にすぎなかったのである[宮沢四七頁以下・六一頁以下、和田四四頁以下、中村八四頁以下、清宮六六頁以下、佐藤四三頁以下、鵜飼三一頁以下、田上八三頁、橋本八八頁以下]。
「欽定憲法説」は、「現憲法においては主權が國民にあるのだから」と云ふ單純な理由で否定されてゐる。
「条約憲法説」「民定憲法説」は現在廣く受容れられてゐる考へだが、何れも故事つけじみてをり、「日本国憲法の制定」を正當化する「爲にする解釋」の印象が強い。一見尤もな「論理」に見える爲、ほぼ全ての法律家・法學研究者が受容れてゐる解釋である。
「条約憲法説」は、所詮「解釋として條約と看做すと説明出來る」と云ふだけの机上の空論でしかない。「条約」を「結んだ」事實が存在しない事が泣き所である。G.H.Q.は自らの干渉を匿さうとしてをり、憲法の改正の場で「外交交渉」が「あつた」と看做される事を囘避しようとしてゐる。
「民定憲法説」は、「革命」は事實として存在しないから、「革命的」な事態なる觀念を構想して説明しようとしたものであるが、三百代言の詭辯としか言ひやうがない。憲法の改正について「革命的」のやうな觀念を以て説明が可能とするならば、ありとあらゆる不當な行爲が「革命的」なる語に據つて正當化されると云ふ大問題を生ずる。また、「無條件降伏」と云ふ建前のポツダム宣言において、主權の移動と云ふ條件が課され得るのか、と云ふ問題も殘る。
何れも「讀めば讀むほど突込みどころが涌いて出て來る」と云ふ「論理」であり、「極めて好意的に接する事によつてのみ受容れ可能」な「解釋」である。この事には反省が必要であらう。吾々は、大日本帝國憲法に對しては極めて冷酷な態度をとり、惡意に基いた解釋を行ふが、「日本国憲法」に對しては極端に寛容で非道く善意の解釋を行ふ、と云ふ傾向がある。
「日本国憲法」が「無罪」とされ「有效である」と確認される爲には、「日本国憲法」に對してこそ惡意で以て接する必要がある。さうした批判を堂々と正面から打破つてこそ「日本国憲法」はその正當性を主張出來ると言ふものである。しかし、さう云ふ態度をとつて「日本国憲法」の強靱さと正當性を主張した論者は一人もゐない。當り前の話で、「日本国憲法」の制定の過程には餘りにも大量の疑義と矛盾とが存する。それら全てに目を瞑る事に據つて、現在の「日本国憲法」の「權威」は成立してゐる。