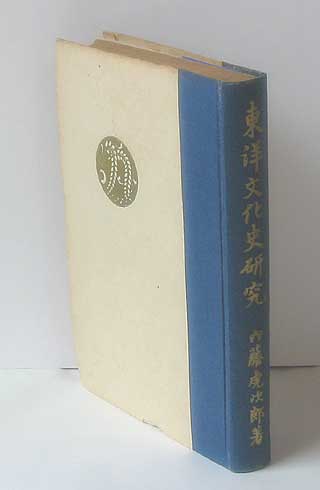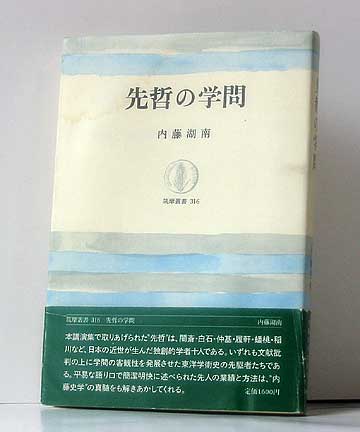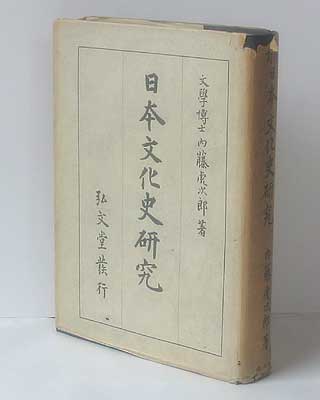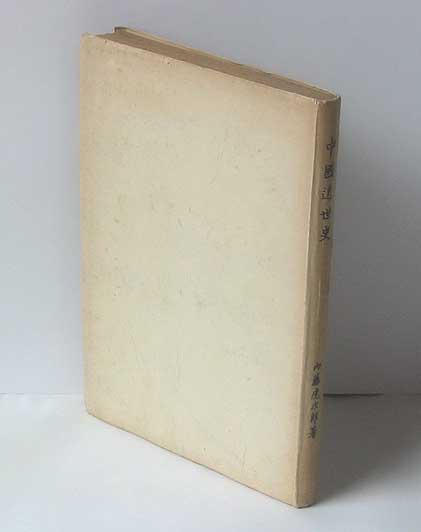- 制作者(webmaster)
- 野嵜健秀(Takehide Nozaki)
- 公開
- 2005-05-15
- 改訂
- 2005-05-22
内藤湖南
- 慶應二(1866)年〜昭和九(1934)年。
- 陸中國鹿角群毛馬内村の生れ。本名虎次郎。湖南と號す。
- 秋田師範學校高等師範科卒業後、一度は教職に就いたが、のち上京、新聞記者となつた。明教新誌、萬報一覽、大同新報、三河新聞、日本人(亞細亞)、大阪朝日新聞、臺灣日報、萬朝報を經てゐる。
- 明治三十八年から朝鮮、滿洲、支那の各地を度々調査・視察。大正十三年から翌年にかけてヨーロッパを旅行。
- 明治四十年、京都帝國大學文科大學講師に招聘され、東洋史學講座を擔任。四十二年から教授。文學博士。同僚と共に京大支那學を全盛に導いた。大正十五年退職。昭和二年、名譽教授。
- 著作は十四卷の全集に纏められてゐる。
著作より
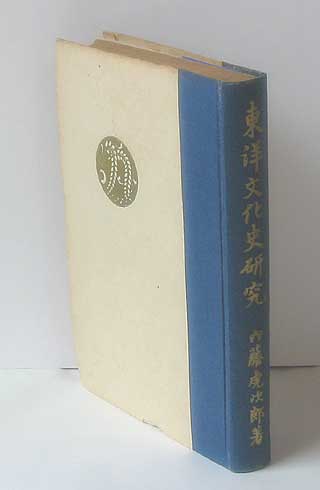
- 昭和十一年三月二十五日初版發行。昭和二十三年四月二十五日八版發行。弘文堂書房。歿後の刊行。序文は羽田亨。
- 目次
- 羽田博士序文
- 凡例
- 支那上古の社會状態
- 殷墟に就て
- 染織に關する文獻の研究
- 北派の書論
- 紙の話
- 支那の通貨としての銀
- 宋元板の話
- 概括的唐宋時代觀
- 近代支那の文化生活
- 支那人の觀たる支那將來觀と其の批評
- 支那に還れ
- 東北亞細亞諸國の感生帝説
- 女眞種屬の同源傳説
- 日本滿洲交通略説
- 古の滿洲と今の滿洲
- 昔の滿洲研究
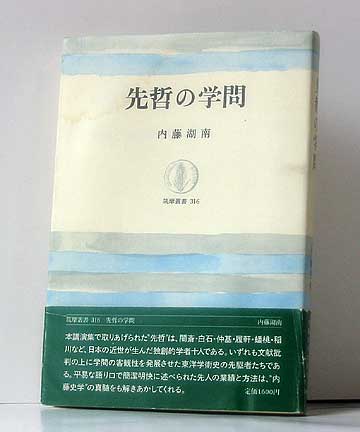
- 1987年9月10日初版第1刷発行。筑摩書房。筑摩叢書316。昭和二十一年五月に弘文堂から刊行された遺著で、のち全集に收められた。筑摩叢書版はその再刊。
- 目次
- 山崎闇斎の學問とその發展
- 白石の一遺聞に就て
- 大阪の町人學者富永仲基
- 慈雲尊者の學問に就て
- 寛政時代の藏書家市橋下総守
- 履軒學の影響
- 山片蟠桃に就て
- 賀茂眞淵翁と山梨稻川先生
- 山梨稻川の學問
- 附録
- 解脱上人の出られた家柄
- 跋
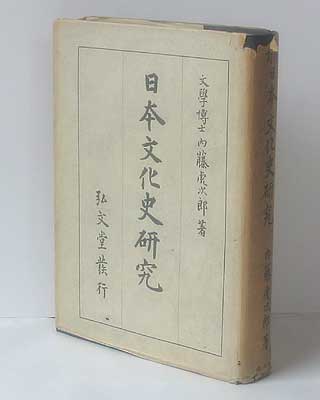
- 大正十三年九月十日第一刷發行。昭和二十一年十月二十五日増訂第八刷發行。弘文堂。講演筆記を纏めたもの。昭和五年末に増訂版刊行。
- 目次
- 日本文化とは何ぞや(其一)
- 日本文化とは何ぞや(其二)
- 日本上古の状態
- 近畿地方に於ける神社
- 聖徳太子
- 弘法大師の文藝
- 平安朝時代の漢文學
- 日本の肖像畫と鎌倉時代
- 日本文化の獨立
- 應仁の亂について
- 大阪の町人と學問
- 維新史の資料に就て
- 増補
- 飛鳥朝の支那文化輸入に就て
- 古寫本日本書紀に就て
- 唐代の文化と天平の文化
- 香の木所に就て
- 日本國民の文化的素質
- 日本文化の獨立と普通教育
- 日本風景觀
- 附録
- 挑戰攻守の形勢
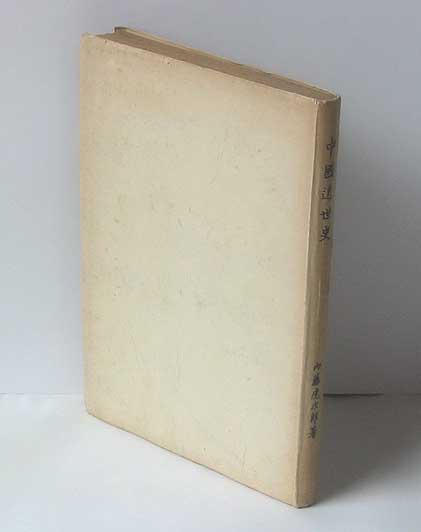
- 昭和二十二年四月二十日初版發行。弘文堂。京都帝國大學における大正九年の講義ノートを補訂したもの。
外部リンク